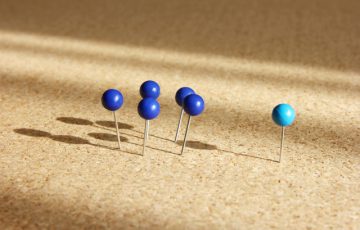いつも明るく元気だった小学生の子どもに異変を感じる。なんだろう、この違和感。あれ?もしかして…仲間はずれになって孤立しているのかな!?それともどうなんだろう?集団生活の中では、みんなと仲良く楽しく過ごして欲しいのに、なんだか小学生の子どものことが気になって仕方がない…
もし、仲間はずれになっているなら、黙ってないで、その気持ちやお友達との関係性を聴かせてほしいのに、なんだかこちら側から聴くのも怖い、心配、モヤモヤ感が湧く親としての立場から小学生の子どもに対して、どう接していいのか思い悩んでいるあなたへ・・・初めての試練を乗り越えるための5つの心理メセッド。
「仲間はずれ」それは本当!?

大切な子どもが、学校で塾で仲間はずれにされているようだ、みんなから離れて、ひとりぼっちで遊んでいる場面を見聞きした、そういうとき、あなたは、とてもビックリして『どうして・・・なぜ?』と、子どものことを心配し、狼狽して、辛く悲しくなりますね。
みんなと仲良く、一緒にいてほしい・・・大切な子どもに対して、あなたも同じように感じていると思います。どこが悪いのか、あれこれ子どもよりも先回りして、何かできることはないかといろいろと考えてしまいます。そして、まだ『仲間はずれ』だと決定してもいないのに、そのように見えるメガネを、あなたが掛けて見てしまうと、本来は、そうではないのにもかかわらず、現実も、そのように見えてしまいます。「仲間はずれって、それは本当?」と、まずは冷静に、自分自身に問いかけてみましょう。
子どもさんの中には、ひとりで遊ぶのが好きとか、みんなと一緒では無くて、ひとりで居る時間を大切にしたくて、仲間から離れたところにいる場合もあります。まずは、すぐに「仲間はずれなの!?」と、決めつけないで、その様子を、よく確認して、子どもさんを信じて見守ってみましょう。
まずは、子どもの気持ちに寄り添ってみよう
もしそれでも、やっぱり「仲間はずれ」だったと確信した場合、あなたの気持ちとしては、ハラハラして、すぐに子どもに対して、「なぜ〇〇ちゃんと遊ばないの?」「あなたの〇〇が悪いからよ!」「もっとしっかりしなさい!」と、厳しく問い詰めてしまったり怒鳴ってしまうこともあります。
そして、どんな経緯があったとしても、お友達に対して、「うちの子を苛めないで!」と注意したり、我が子かわいさに、「どうしてくれるのよ!」と、いたたまれなくなったあなたは、強い口調で仲間はずれにした子どもさんの親や先生に対して抗議してしまいがちですが、これは子ども同士の問題です。
小学生とはいえ、自分で解決できる力があります。それを、あなたがすぐに介入して、子どもの話を聴かずに解決してしまうと、その時は良いのですが、この先の長い人生で、もし同じことが繰り返されたとき、自分自身で解決できずに成長してしまい、大人になってからも同じ悩みで苦しんでしまいます。
子どもが普段と違って、様子がおかしく元気がないときは、『なにがあったの?』『どうしたの?』と優しく声をかけてみましょう。子どもは、そこでは何も話してくれないかもしれません。その時は、子どもを信じて、普段と変わりないように接して見守りましょう。ただし、『なにがあっても、いつでもお母さん(お父さん)は、あなたの味方よ』と、子どもと目と目を合わせて、手を繋いだり握って、そっと抱きしめて優しく伝えてあげましょう。
「仲間はずれ」は、典型的ないじめ行為であり、どの子どもたちにも起きうるものです。それゆえ、もし我が子が「仲間はずれ」になったとしたら、『あなたは何も悪くない』と伝えてあげましょう。間違っても、「あなたも悪かったんじゃない」は、NGです。子どもを疑い責めて、仲間はずれを容認することになり子どもは、より心を閉ざしてしまいます。
心理的に子どもは「親に認めてもらう」ことを優先的に考え行動する
「仲間はずれ」って、いきなり始まったりするものです。なので、本人としては訳がわからず、とまどいを感じます。それが小学生なら尚更のことです。昨日まで仲良くしていたのにどうして・・・?と、悲しみや怒りの感情も湧きあがります。仲間はずれの仕方にもいろいろありますが、まず子どもは、そのことで親であるあなたに、心配をかけたくないという気持ちやあなたに知られてしまったら恥ずかしいという気持ちをいだきます。
また、こんな自分が惨めに感じて、そんな姿を、あなたに見せてしまったら、大好きなあなたからも、嫌われてしまうんじゃないかという不安を抱えて、自分なんか・・・という自己否定をしてしまいがちです。それゆえ、もしお子さんが、つらい気持ちを正直に話してくれたら、『話してくれてありがとう』と、その勇気をねぎらい、子どもとともに戸惑いや悲しみ、怒りを共有し、はっきりと『仲間はずれは精神的な暴力だ!!』と伝えましょう。
精神的な暴力を受けて「つらい」「悲しい」と思うことは、誰にとっても当たり前のことであり、それによって、『子ども自身の価値は、何も変わらない』ということと、その時に感じたありのままの気持ちを、『正直に周りに言っていいんだよ』と、心に深い傷を残さないように、お子さんに対して愛の言葉を伝えてあげましょう。もしあなたが、先生に相談して介入してもらう時は、必ず子どもからの許可を取ってからにしましょう。
子どもを変えようとするのではなく…まずは認めてみよう
小学生の子どもが、「仲間はずれ」にされてしまうと、子育てに自信を無くしてしまうかもしれません。そして、子どものどこが悪かったのかと考えてしまいがちですが、それはもしかしたら、『すべての人に好かれなければならない』という、親であるあなたの思い込みが、根元にあるからではありませんか?
日本は、調和を重んじる協調性の高い素晴らしい文化を持っていますが、個性というのを認める文化ではありません。だから、ありのままに、「あり~のままに~」と、アナと雪の女王がどんなに流行っても日本人は、ありのままにって何?っていうくらい、ありのままが解らなかったりします。
それは個性というものを認める文化ではなかったからです。みんなと一緒が普通。協調性、調和を重んじるため、はみ出し者は、変わり者とみなされ仲間はずれの対象になってしまうおそれがあったからです。あなたも、もしかしたら子ども時代に、みんなと同じようにしていないと、周りから注意されたり怒られた経験やトラウマをお持ちではありませんか?もしくは、はみ出し者、変わり者とみなされるのが怖くて、一生懸命、自分を押し殺し我慢して、みんなと同じようにしていませんか?
たしかに、日常で共同生活を送る場所では、規則や社会のルールを守ることは大切なことであり必要ですが、それさえ守っていれば、全てをみんなと一緒にする必要はないのです。あなたのその経験やトラウマを通して、つい子どものことが気になってしまい、口を出してしてしまうのは、あなたの優しさでもありますが、それよりも、みんなとは違う面を持ったところを認めて、これが子どもの『才能』であり『個性』だという見方をしてあげてください。
子どもは、あなたのモノではなく、立派な感情を持った1人の人格者です。子どもの為に、何とかしたいという思いが強くなりすぎて、想い通りにコントロールしようとしても、いずれは不可能になります。そして、すべての人に対して、好かれることには無理があります。
それよりも、子どもの良い面、出来た面を認めてあげましょう。それには、なにをしたかではなく、何の前触れもなく無条件に愛を伝え、子どもの存在に語りかけていけばいいのです。『〇〇ができたから~ではなく、〇〇ができても、〇〇ができなくてもOK』という承認方法です。
これにより、白か黒か良いか悪いかといった二極化ではなく、より多くの選択肢をもつことにより、ご自身の頭で考え、ご自身で選択する力がつきます。小学生のうちに、たくさんの経験をさせることにより、同じような場面に遭遇したとき、嫌な気持ちを感じたときに、すぐに自らの力で上手く切り抜け、乗り越える力がついたり立ち直れるように、お友達との関係性を通して積み重ねていく冒険の時期だと考えてみてはいかがでしょうか。
子どもの安全基地を作ろう!
そうは言っても、学校や塾で息抜きが出来ずに緊張感にさいなまれていたり、孤立を強いられ寂しい思いをしている子どもにとって家庭やあなたは、唯一の味方であり、ホッとできる居心地のよい安全基地であることが重要になります。仲間はずれにされている本人は、大変につらく地獄のような毎日を耐えているものです。
そして、小学生の子どもでも、あなたが思う以上に、あなたのことをよく観察しています。心配させたくない!仲間はずれにされていると思われたくない!悔しい気持ちを表面に出していいのか、泣いて感情を出していいのか、甘えてもいいのか・・・など、たくさんのことを考えています。
子ども自身が、あなたに対して受け入れらているか確かめる行動に出ることもあります。そのときは、いっぱい甘えさせて安心感を持たせ、子どもの気持ちを、おだやかに安定させて、自分は大切で価値ある存在だ!という自己肯定感を与えましょう。『何があっても、あなたのことが大好きだよ、大丈夫!』と伝えてあげてください。
尚、甘えと過干渉は違います。甘えは、安心感をはぐくみ、子どもが子どもらしくいられる環境を作るのに対して、過干渉とは、親の都合を勝手に、子どもの意思とは関係なく押し付けます。
まとめ
小学生の頃は、多くのお友達を作ることが素晴らしいことのように刷り込みされ、お友達は誰とでも仲良くするのが大事という価値観を植えつけられ集団生活に耐えることを強いられてしまいます。それによって、そこから、一旦はみ出してしまうと、これから先もずっと辛い人間関係が待ち受けているように感じてしまいますが、長い人生を振り返ってみたときに、小学生時代のお友達が今でも仲良く繋がって、重要な立場の関係であることは少ないような気が致します。
それならば、集団生活の中でおこった『仲間はずれ』という1つの経験を通して、可愛い我が子に旅をさせるつもりで、小学生の時から子どもさん自身の力を試してみる良い期間と捉えてみたらどうでしょうか。
こちらの記事もご覧ください。⇒幼少期の親子関係について~仲間はずれ等の問題行動をするお子さんの背景